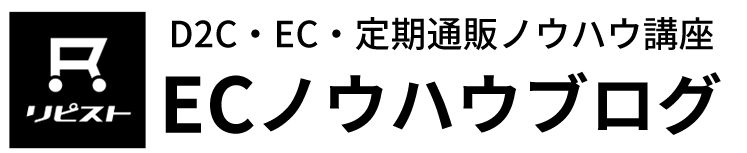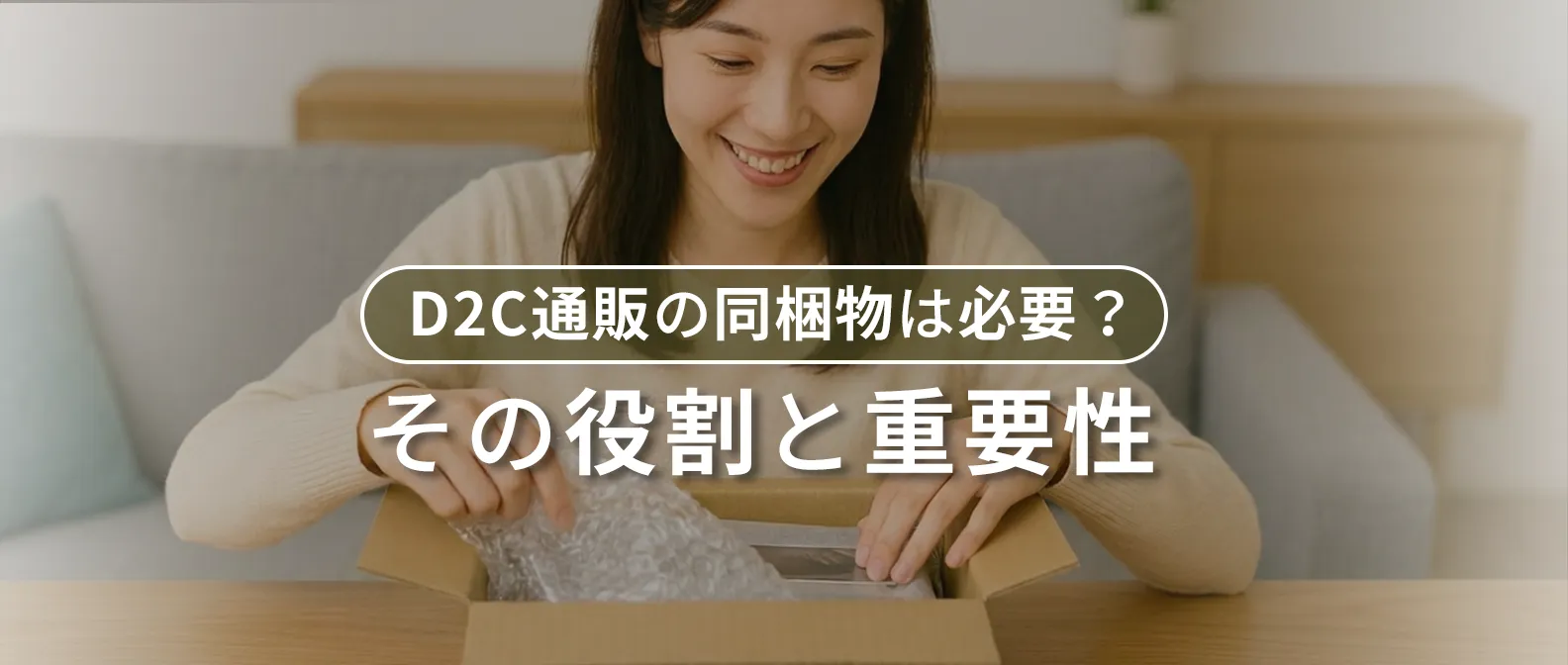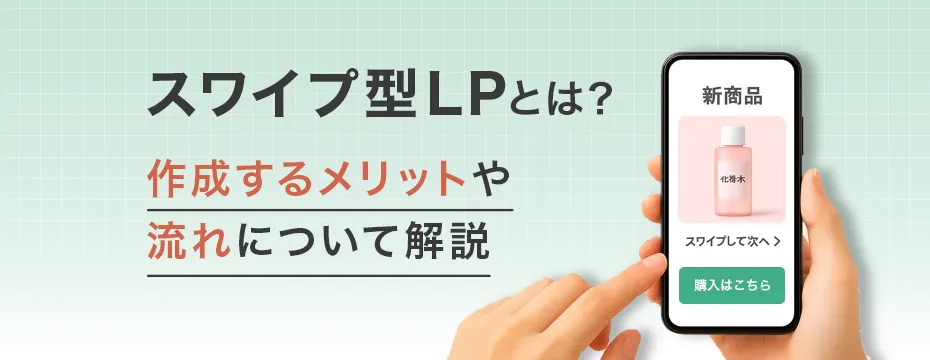OMOとは?D2Cブランドが押さえるべき基礎知識と活用方法を紹介

近年注目されているOMOは、ECサイトと実店舗を融合させた新しいビジネスモデルで、多くのD2Cブランドが活用してLTVや売上の向上をサポートしています。
本記事では、OMOの基本的な意味やオムニチャネルとの違いや導入によるメリット、具体的な方法にくわえて、導入時の注意点をわかりやすく解説。さらに、成功事例も紹介します。
OMOの概要や意味

OMO(Online Merges with Offline)は、オンラインとオフラインを組分けせずに活用して売上を向上させるマーケティング手法です。OMOはこれまでECサイトで手軽に買い物をし、実店舗で商品を手にとって買い物をするスタイルを個別に運営していた形態から、顧客が双方の手段を横断して利用できるスタイルを目指します。
例えば、オンラインで商品を検索して店舗に来店を促したり、店舗で見た商品をオンラインの購入に結びつける施策などが含まれます。
OMOの最大のメリットは、ECサイトと実店舗のデータを統合することで、顧客体験の向上や売上の最大化を実現できる点です。顧客体験を最大化することで、D2Cブランドは顧客との関係性を深め、より効果的なマーケティングが可能になります。
オムニチャネルやO2Oの違いは?
オムニチャネルは複数の販売チャネルを統合し、顧客がどのチャネルを利用しても一貫した体験を提供する手法です。オムニチャネルはECサイトや実店舗、スマホアプリ、カタログ通販など、すべてのチャネルが連携している状態を目指し、「一貫性」に重点を置いてビジネスを行います。
一方、O2O(Online to Offline)は、オンラインでのマーケティング施策を通して、顧客をオフラインの実店舗に誘導する施策を指します。クーポン配布や店舗在庫の確認機能などを実施してオンラインとオフラインが双方向に融合し、単なる誘導に留まらない販売形態をを目指します。
OMOを活用時に与えるD2Cブランドへの影響

OMOはD2Cブランドにとって、ECと実店舗の両方の強みを生かし、顧客体験を向上させる重要な手法です。以下では、OMO活用時に与えるD2Cブランドへの影響やメリットを解説します。
販売チャネルに多岐に渡り事業全体の売上が上がりやすくなる
OMOを導入すると、オンラインとオフラインが連携されて、顧客にとって買い物をしやすい環境を提供でき、売上が上がりやすくなります。
例えば、オンライン上で商品を購入した商品を自宅に配送するか店舗受け取りにできるようにしたり、店舗の在庫状況をECサイトで確認できる仕組みを導入したりすることで、買い物の利便性が向上します。
配送時間が発生することによる離脱を防ぎやすい
ECサイトは、配送時間がかかることが離脱の一因となることがあります。OMOを活用して、店舗受け取りや即時配送サービスを提供することで顧客が配送時間を待たずに商品を手にすることが可能です。
配送時間を短縮することで「すぐに商品が欲しい」というニーズを持つ顧客のニーズを満たすことができます。
OMOを導入する方法は?

OMOを成功させるには、計画的にシステムを導入したり、オンラインとオフラインを融合した施策を実行したりする必要があります。
導入の際は現状の課題と課題を解決する方法を洗い出し、適切なシステムやツールを組み合わせることが大切です。ここからは、導入プロセスのポイントを解説します。
現状の課題と解決できる顧客体験を割り出す
まず、自社の顧客体験における課題を明確にします。例えば「オンラインとオフラインの在庫を一貫して見れない」「配送に時間がかかり、ECサイトのカゴ落ちが増えている」などの課題が挙げられるでしょう。
上記の課題に対して、OMOを駆使した課題解決方法や、顧客満足度を向上させる施策を計画します。例えば、店舗での接客データを活用したECサイトのパーソナライズ化や、オンラインでの在庫確認を可能にする施策、来店用クーポンの導入などおすすめです。
実店舗とECサイトの在庫管理できるカートシステムを導入する
OMOを実現するには、実店舗とECサイトの在庫を一元管理できるカートシステムの導入が必須です。対応するカートシステムを導入することで、顧客がオンラインで在庫状況を確認した後、店舗で受取をできる「クリック&コレクト」などの施策をスムーズに展開できます。
また、在庫を一元管理できることで近隣店舗への来店や後日のオンライン購入も促せるため、商品の購入を検討している顧客層へのアプローチがしやすくなります。
カートシステム以外のツールの整理・導入も行うこと
OMOを導入する際は、カートシステムだけでなく、CRM(顧客管理システム)やMA(マーケティングオートメーション)ツール、POSシステムなどの各種ツールを整理し、連携させることも重要です。
各データを連携することでオンラインとオフラインで得られるデータを統合することで、ECサイトと実店舗の売上や人気商品の比較や分析を簡単に行えます。また、実店舗のデータを簡単に見れるため、店舗のエリアマネージャーやマーケティング担当者のリソースの削減につなげるのもメリットです。
OMO導入で気をつけるべきポイント

OMOの導入には、単にツールを導入するだけではなく、システムや施策を適切に運用し、顧客体験を最適化することが求められます。以下の、注意ポイントを確認して、OMOの導入に役立ててください。
実店舗とECの情報を連携できるカートシステムを使うこと
OMO導入後は、実店舗とECサイトの情報をスムーズに連携させることが重要です。カートシステム内にデータ連携の機能がない場合は、外部サービスを取り込んでデータを連携できるか、必ず確認しましょう。
外部サービスを使うことで、カートシステムの乗り換え時も操作の見直しやデータのインポートなどを行わずにOMOを導入することができます。
さまざまな手法の顧客体験を導入してテストすること
OMO施策を成功させるためには、さまざまな施策を行い、効果検証することが重要です。例えば、クリック&コレクト導入後の売上の変化や限定クーポンの利用率などを見ることで、顧客にとって必要な機能や売上の変化を見ることができます。
実店舗の変化を検証する場合はアンケートやSNSのキャンペーンの併用をするのがおすすめです。ECサイトの場合はヒートマップのクリック箇所や各ページのPV数などを見て分析を行うと良いでしょう。
広告はWebとオフラインどちらもおすすめ
OMO導入後の広告は、Web広告とオフライン広告を併用しましょう。Web広告ではCV数(コンバージョン数)を追い、オフライン広告では配信後の店舗来客数やサイトPV数、SNSフォロワー数を測定します。各データを統合して広告効果を分析することで、次の施策に活用できます。
OMO導入時は多くのツールと連携できる「リピストX」がおすすめ

OMOを実現するためには、多くのシステムやツールを連携させて効果測定をしながら行うことが重要です。「リピストX」は、ECサイトの制作が初めてな企業様におすすめの設定代行や運営アドバイスや、各ツールの連携に対応しています。
効率的でスムーズなOMO導入を目指す方は、ぜひ「リピストX」を活用してみてください。
お問い合わせはこちら
EC通販に精通したプロがお答えいたします。